「相続財産が土地や株などの有価証券だけで現金が手元にない」など
相続したものの、さまざまな理由で相続税を払えないかもと悩んでいませんか?
実は相続税を払えない場合にはいくつかの対処法があります。
それは
- 延納を利用する
- 物納を利用する
- 相続財産を売却して納税資金を確保する
- 納税資金を借り入れする
- 相続放棄
の5つです。
この記事では、それぞれの対処法をとるための要件やメリット・デメリットを解説します。
ご自身に適切な対処法をみつけて早めに手続きをとりましょう。
延納を利用する

相続税は現金一括での納付が原則です。
しかし、期日までにお支払いができない場合には、分割で支払っていく「延納」という制度を利用できます。
延納制度を利用するには申告期限までに申請する必要があるので注意しましょう。
分割期間は原則5年以内ですが、相続財産による現金が少ない場合や、不動産に占める割合が大きいなどの条件を満たすと最長で20年まで認められ、申請要件は以下の通りです。
延納の要件
- 相続税額が10万円を超えている。
- 現金一括で納付することが困難とする理由があり、その納付を困難とする金額の範囲内である。
- 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供する。
※ただし、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 - 延納申請にかかる相続税の納付期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、「延納申請書」と「担保提供関係書類」を提出する。
参考元:国税庁/相続税の延納
延納のメリット
- 一括ではなく分割のため、支払いの負担が軽くなる
- 支払いのため、大事な財産を手放さなくてよくなる
分割払いできることによって、一度に多額のお金を支払わなくて済むため家計に余裕ができるでしょう。
延納のデメリット
- 延納期間中は利子税の納付が必要となり、実際の納付額より高くなる。
- 延納の担保として財産の提供が求められる
延納期間が長くなればなるほど支払総額は高くなります。
計画的にできる限り早めの納付をしましょう。
延納期間や利子税の詳細は以下の通りです。
| 区分 | 延納期間
(最高) |
延納利子税割合
(年割合) |
|
| 不動産等の割合が 75%以上 |
①動産等にかかる延納相続税額 | 10年 | 5.4% |
| ②不動産等にかかる延納相続税額(③を除く) | 20年 | 3.6% | |
| ③森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木にかかる延納相続税額 | 20年 | 1.2% | |
| 不動産等の割合が50%以上
75%未満 |
④動産等にかかる延納相続税額 | 10年 | 5.4% |
| ⑤不動産等にかかる延納相続税額(⑥を除く) | 15年 | 3.6% | |
| ⑥森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木にかかる延納相続税額 | 20年 | 1.2% | |
| 不動産等の割合が50%未満 | ⑦一般の延納相続税額(⑧、⑨および⑩を除く) | 5年 | 6.0% |
| ⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(⑩を除く) | 5年 | 4.8% | |
| ⑨特別緑地保全地区等内の土地にかかる延納相続税額 | 5年 | 4.2% | |
| ⑩森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木にかかる延納相続税額 | 5年 | 1.2% | |
引用元:国税庁/相続税の延納
物納を利用する

延納での納付が難しい場合は、納税者の申請により土地などの不動産や株などの有価証券の現物で納付する「物納」という制度を利用できます。
物納は相続税のみで利用できる制度で、相続税の申告期限までに税務署へ提出しなければなりません。期限を過ぎると認められませんので注意しましょう。
物納を利用する要件は以下の通りです。
物納の要件
1)延納で納付することを困難とする事由があり、その納付を困難とする金額を限度としている。
(2)物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、下記の財産および順位(1から5の順)で、その所在が日本国内にあること。
<第1順位>
1 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
2 不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
<第2順位>
3 非上場株式等
4 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
<第3順位>
5 動産
参考元:国税庁/相続税の物納
物納のメリット
- 相続した土地などの不動産や株などの有価証券をそのまま納められる
物納は一括納付や延納でも難しい場合の選択肢になるため、万が一相続財産の現金・預貯金の割合が少ない場合に利用できるのが最大のメリットです。
物納のデメリット
- 物納する財産は自分で決められない
- 物納財産は時価よりも安い「相続税評価額」にて評価される
相続税評価額は時価の0.8掛け程度になるため、時価よりも低い金額での納付になり、物納が認められるまでの期間にも「利子税」課されます。
相続財産を売却して納税資金を確保する

ご自身や相続財産の現金・預貯金が少ない場合には相続財産を売却し現金化して相続税を支払うという方法があります。
株式などの有価証券であれば、流動性が高いため売却して現金化することは簡単です。
しかし土地などの不動産は相続する方に名義を変更する手続き(所有権移転登記)や流動性の問題で買い手が見つかりにくい場合があります。
相続税の納付期日は決まっているため売却する際は早めに手続きをとりましょう。
相続財産売却のメリット
- 相続税評価額よりも高く売却できる可能性が高い
- 譲渡所得税などを軽減できる特例が適用される
高額で売却できれば物納より断然有利となります。
売却金額に譲渡所得税という税金はかかりますが特例適用されるなど、
手取り金額を把握したうえで売却することをおすすめします。
相続財産売却のデメリット
- 納税期限までに売却できない可能性がある
- 相続税評価額よりも安い金額で売却する可能性がある
一番気をつけなければならないことは納税期限までに売却できるかどうかです。
また売り急ぎにより相続税評価額よりも安くなり、税金など諸経費もかかるため手続きを含め計画的に売却することをおすすめします。
納税資金を借り入れする

相続税を支払う方法として金融機関から借り入れすることも1つの方法です。
不動産などの売却で納税資金を確保する予定が売却相手が見つからない場合などに、不動産などを担保に借り入れできるか確認することをおすすめします。
また、納税資金として借り入れできる商品もあるので1つの選択肢として持っておきましょう。
納税資金を借り入れするメリット
- 不動産を売り急ぐ必要がなくなる
- 納税資金としてすぐに用意できる
気をつけなければならにのは売り急ぎによる安価での売却です。
また、借り入れすることで計画的に返済できますが、延納と比べて高くならないように気をつけましょう。
納税資金を借り入れするデメリット
- 借り入れには審査がある
- 借り入れ際には利息がつく
借り入れには審査があるため、借りれる前提で行動しないようにしましょう。
借り入れできる時期も確認するなど、納付期日に間に合うよう計画的に手続きすることをおすすめします。
相続放棄

相続放棄とは、その名の通りすべての相続財産を放棄することで、
相続放棄をする最大のメリットは、マイナスの財産を負わなくて良くなることです。
もし相続財産に借金が多く含まれる場合には相続放棄を選択するのも1つの方法でしょう。
相続放棄を選択する場合は状況をしっかり見極めることをおすすめします。

まとめ

今回は相続税が払えない場合の対処法を解説しました。
相続税が払えない場合は人によって異なります。
それぞれの状況に適した対処法を見極めることが重要です。
この記事で解説した5つの対処法
- 延納を利用する
- 物納を利用する
- 相続財産を売却して納税資金を確保する
- 納税資金を借り入れする
- 相続放棄
を参考にしてください。
それぞれの対処法には細かい条件があるため自分のみでの判断ではなく、
弁護士や税理士などの専門家に相談することもおすすめです。
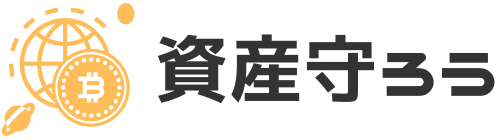









コメント