「年金保険料を払えないとどのようなリスクがあるのか」
「年金保険料を払えなくなった時に利用できる救済制度はないの」
失業や休業などによって収入が減少し、保険料を納付できないという人も多いと思います。
しかし年金保険料を払わないと財産の差し押さえや年金を受けることができないリスクがあることを忘れてはいけません。それでは年金保険料の未納を防ぐためにはどのような対策が必要になるのか。
今回は保険料を払えない際に活用できる免除制度や納付猶予制度の基準について解説します。
年金保険料を払えないとどうなるか

年金保険料を払えない期間が続いてしまった場合どのような事態が想定されるのでしょうか。短期的には財産の差し押さえの可能性が、長期的には将来年金が受け取れないリスクが考えられます。
特別な事情があり納付ができないケースでは国の救済制度を利用することができますが、原則として支払う義務があります。
財産の差し押さえに発展する場合も
年金保険料の未納が続いた場合には、最終的に財産の差し押さえられてしまう可能性があります。ここでは差し押さえまでの流れや仕組みについてみていきましょう。
納付督励
年金保険料の未納が続いた場合、日本年金機構から電話や書類によって保険料の自主納付を促す納付督励が行われます。納付督励の時点では、年金保険料の支払いを忘れていないか確認をする程度で済むので、通知が送られたタイミングで年金保険料を完納することができれば問題ありません。
しかし納付督励の通知がされても納付を行わない場合には特別催告状が送られてきます。
特別催告状では青→黄→赤のように、封筒の色によって危険度が変わる仕組みになっています。特に赤色の特別催告状は財産差し押さえに関する情報が記載されているため早急に納付する必要があります。
最終催告状の送付
特別催告状の通知が行われた後も納付を怠っていると、最終催告状が送付されます。最終催告状にはこれまでの未納分の納付書と、期限内に納付がされなかった場合に財産の差し押さえを開始することが書かれています。
最終催告状は強制徴収に当てはまる人だけにしか送付されません。これまでより危険度が上がるため納付が可能な人は即時手続きを行いましょう。
督促状の送付
最終催告状の期限までに納付がされなかった場合には督促状が送付されます。督促状では期限内の支払いがされなかった際に財産の差し押さえが行われる事以外にも、延滞金が発生することや、配偶者や家族などの連帯滞納義務者の財産の差し押さえに関しての情報も記載されています。
財産の差し押さえ
督促状や差し押さえの予告上の期限内に納付を行わないと財産差し押さえが行われます。
差し押さえされる資産の種類には、給料や銀行預金、有価証券、不動産、自動車など、対象者の財政調査が行われ、強制的に年金を徴収します。
また差し押さえの対象者は未納者以外にも世帯主や配偶者などの家族にも及ぶことになるので注意しましょう。
財産の差し押さえの過程で職場や金融機関、家族にも知られてしまうため社会的信用が落ちてしまいます。このような事態をさけるために年金保険料の未納分は早めに納付する必要があることを覚えておきましょう。
将来年金を受け取れない可能性
年金を払えない期間が続くと将来年金を受け取れなくなったり減額される可能性があります。
年金を受け取るためには年金保険料の納付期間が10年以上でないといけません。仮に納付期間が10年未満の場合には年金を受け取れないので損をしてしまいます。また将来の年金受給額は年金保険料の納付期間の長さや納付金額に比例します。つまり年金保険料の未納期間が長いほど将来の年金も減額されるため、少しでも納付できるよう気を付ける必要があります。
年金保険料が払えないときに使える制度
収入が安定していなかったり失業などによって年金保険料を払えない場合には、年金保険料の免除や納付猶予制度を積極的に利用しましょう。仮に年金保険料が未納の期間中に事故や病気、怪我などに遭った場合に遺族年金や障害年金を受け取ることができない可能性があります。そこで年金保険料の免除・納付猶予制度を有効に活用することで期間中に不測の事態が生じた際にもリスクを回避することが可能です。
保険免除制度
保険免除制度は、本人や世帯主、配偶者などが失業した場合や前年の所得が一定額以下の場合に申請することができます。申請が承認された全ての人が全額免除されるわけではなく、基準に応じて4種類の免除割合に分けられます。
| 免除の種類 | 前年の所得基準 |
| 全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
| 4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
扶養親族等控除額や社会保険料控除額はどちらも確定申告で必要になる情報であるため、分からない場合は確定申告書の控えや源泉徴収票で確認しましょう。
保険納付猶予制度
一方で納付猶予制度とは国民年金保険料の納付が困難な50歳未満の方を対象としています。免除制度とは違い申請者本人と配偶者の所得基準で判断され、世帯主がいたとしても審査の対象にはならないため免除制度よりも申請するハードルは下がることになります。
| 前年の所得基準 | |
| 納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
上記のように納付猶予が承認されるためには、全額免除と同じ基準を満たしている必要があることに注意しましょう。
年金保険料の免除制度と納付猶予制度の違いを理解する
上記で紹介した年金保険料の免除と納付猶予の制度は、どちらも年金保険料の未納を防ぐための手段ですが違いを理解することも大事です。
| 免除 | 納付猶予 | |
| 申請が可能な人 | 20歳以上60歳未満 | 20歳以上50歳未満 |
| 審査の対象者 | 申請者、配偶者、世帯主 | 申請者、配偶者 |
| 年金受給資格期間 | 含まれる | 含まれる |
| 年金額への算入 | 全額免除:50%4分の3免除:62.5%半額免除:75%4分の1免除:87.5% | 含まれない |
保険料の免除では60歳まで申請が可能であることに対し、納付猶予では将来的に追納が期待できる50歳までと申請できる年齢に違いがあります。また納付猶予制度は年金の受給資格期間は算入がされますが、将来受け取ることができる年金額への反映はされません。年金額の減額を回避したい場合には猶予期間分の追納を行う必要があることに注意しましょう。
年金保険料の免除・納付猶予制度を利用する際の注意点
救済制度は経済的に苦しくなっても誰でも利用できるわけではありません。また年金額への算入がされない制度を利用していると、追納しない場合に年金受給額が減額されてしまいます。ここでは制度を利用する際の注意点についてみていきましょう。
申請が却下される場合がある
年金保険料の免除・納付猶予制度は明確な基準が定められています。現在の収入が低下しており納付が困難というだけで必ず申請が承認されるわけではありません。具体的には、申請者の前年の年収が基準に達していない場合や、申請者本人の年収に問題がなくても他の配偶者や世帯主が高年収である場合には申請が却下されます。
年金保険料の免除や納付猶予の申請を行う前に前年の収入や申請可能期間などの条件をしっかりと確認をしましょう。
追納することで年金の減額を防ぐ
年金保険料の一部免除や納付猶予制度を受けた後に追納をすることが可能です。追納を行うことで将来の年金受給額を満額に近づけることができます。
注意したいのは追納には10年以内という期間が定められていることです。免除制度や納付猶予制度を利用した期間をしっかりと把握しておき、できるだけ早い時期に追納を検討しましょう。
まとめ
今回は年金保険料を払えない時の国による救済制度の仕組みについて解説をしました。
年金保険料を納付しないと財産の差し押さえや老後の年金受給額の減額、障害年金や遺族年金を受け取れないリスクがあります。
生活が苦しくなり年金保険料が払えなくなったら免除や納付猶予制度を積極的に活用し、不測の事態が生じたときに対応できるようにしましょう。
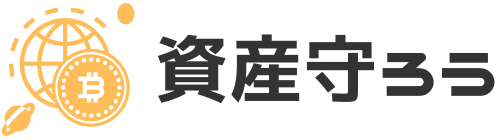









コメント