さまざまな節約術を試してみたけど全然続かなくて貯金できないと悩んでいませんか?
節約と聞くと、やりたいことや食べたいものを我慢するイメージがあります。実は無理せずにお金を使わない節約術があります。
代表的なものは以下の4つです。
- 家計簿をつける
- 固定費を見直す
- 支払いをクレジットカードにする
- ふるさと納税を利用する
この記事では、具体的にどの程度の節約ができ、お金を貯められるのかのシミュレーションとそれぞれのおすすめの方法を解説します。
家計簿をつける
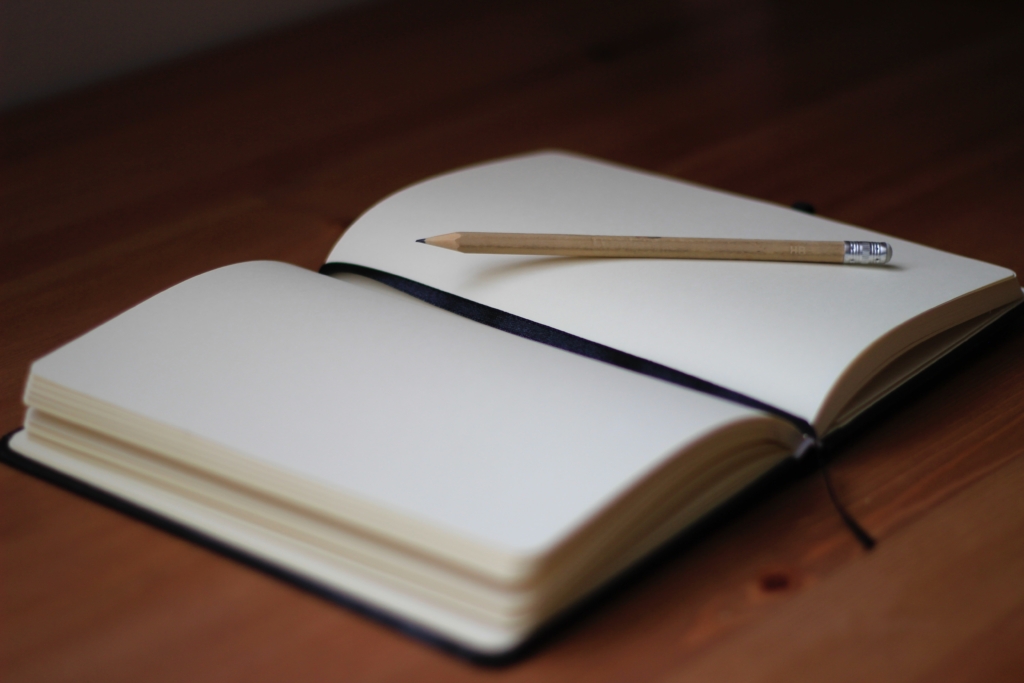
節約してお金を貯めるには、いくらお金が入ってきていくらお金が出て行っているのかの収支を把握する必要があります。
「そんなことわかっているけどめんどくさい」と思う方は家計簿アプリを使うのがおすすめです。
家計簿アプリでは銀行口座やクレジットカードを自動連携することで勝手に収支を計算してくれます。
現金払いの会計では、レシート読み取り機能で簡単にデータ取り入れられるなど、これまで手書きで家計簿を付けていた頃とは比べ物にならないくらい便利です。

固定費を見直す

固定費は毎月、もしくは毎年当たり前のように払っているからこそ見落としがちです。
まずは固定費がもっと安く抑えられないかを見直しましょう。
特に以下の5つを見直すことで大きく節約ができます。
- 住居費用
- 水道光熱費
- 通信費
- 保険料
- サブスクリプション
トータルで月に1万円節約できた場合だと年間12万円、10年では120万円です。
固定費を見直す場合は、短期間ではなく長期間で考えるようにしましょう。
住居費用
固定費の中でももっとも負担の大きいのが家賃や住宅ローンなどの住居費用です。
賃貸の場合は、同じ条件にてもっと安いところはないのか、もしくはいま借りている場所は収入に見合っているか見直す必要があります。
また、会社の寮や借り上げアパートなどの福利厚生を利用することで住宅費用をさらに抑えることをおすすめします。
住宅購入に伴い住宅ローンを借りている場合は、借り換えをすることで今よりも良い金利になるか相談してみましょう。
水道光熱費
水道光熱費は毎月当たり前のように使っているため、特段気にしない方も多いのではないでしょうか。
誰かと比べるものでもないので、目安が分かりません。
そこで、総務省が公表している家計調査による世帯人員別における光熱費の月額平均が以下の通りです。
| 世帯人員 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
| 電気代 | 5,482 | 9,183 | 10,655 | 11,376 |
| ガス代 | 3,001 | 4,330 | 4,930 | 4,882 |
| 他の光熱費 | 651 | 1,331 | 1,169 | 754 |
| 上下水道料 | 2,248 | 4,344 | 5,749 | 6,465 |
| 合計 | 11,383 | 19,168 | 22,503 | 23,477 |
目安がわかったら、電力会社の乗り換えを検討しましょう。
「電力会社の乗り換え?そんなの面倒くさい」と感じる方もいるでしょう。
しかし、電力会社の乗り換えは
- 契約中の会社に解約届不要
- 乗り換え先の会社にネットで申し込む
これだけでカンタンに乗り換えられます。
方法は、
- 検針票や電力会社のWebサイトで毎月の電気使用料と金額を確認する
- 比較サイトで料金をシミュレーションする
- 乗り換え先の会社に申し込みする
この3つのステップで完了です。
特に節電を意識するわけでもなく乗り換えするだけで、月に約1,000円、長い期間で考えると大きな節約になります。
通信費
大手キャリアを契約している方は今すぐ格安SIMに乗り換えることをおすすめします。
「格安SIMは通信品質が悪い」と思われる方もいますが、格安SIMは大手キャリアの回線をレンタルしているため、電波が届かなくなる心配はありません。
通信速度に関しては、若干遅くなる時間帯もありますが、普段使いしていて困ることはないでしょう。
最近では他社の格安SIMに対抗して、大手キャリアも格安プランを提供しています。
docomo(ドコモ)⇒ahamo(アハモ)
au⇒povo(ポヴォ)
ソフトバンク⇒LINEMO(ラインモ)
どれも20GBで約3,000円と、通常プランと比べて約4,000円変わる場合もあり、
一度各社のホームページで料金をシミュレーションしましょう。
保険料
保険には公的保険と民間保険があります。
公的保険は日本人全員が加入しており、公的保険ではカバーできないところを民間保険で対応するのが一般的です。
民間保険に入って以降、担当者に言われるがまま見直しはしていない。
そんな方は今すぐ保険を見直すことをおすすめします。
見直す際には以下の3つを意識しましょう。
- 不要な特約は外す
- 保険料は適正か
- 複数の保険会社を比較する
保険は万が一の時に備えるものですが、その万が一の時にどのくらいのお金が必要なのか理解した上で加入しましょう。
また、公的保険はどういった保障があるかを理解すると不要な民間保険が見えてきます。
意外に知らない公的保険の特徴4選
- 医療費は原則3割負担
- 自己負担の上限金額は月10万円程度(高額医療制度)※年齢・収入水準で決まる
- 病気やケガで働けなくなっても最大1年6か月は保障がある(傷病手当金)
- 保険料は会社と折半(扶養家族の分は無料)
サブスクリプション
サブスクリプションサービスに加入して、ついそのまんまのことが多々あります。
加入しているサービスで不要なものは解約しましょう。
「これ必要なのかな?」と悩んだ場合は一度解約。
数か月後に必要だなと感じたら再加入できるのもサブスクリプションのメリットです。
また無料でできることも多くなっているので定期的に見直すことをおすすめします。
支払い方法をキャッシュレスにする

日本のキャッシュレス比率は2020年現在で約30%と言われており、3人に2人以上が現金で支払いをおこなっています。
例えば、お支払い方法をクレジットカードにすることで月15万円を利用する場合、1500円分のポイントが貯まり、年間で6000円を節約できます。※ポイント還元率1%の場合
「クレジットカードは不正利用が怖い」と思われている方も多いですが、正しい手続きをすることで不正利用分は帰ってくることがほとんどです。
まだ、クレジットカードをお持ちでない方は検討することをおすすめします。

ふるさと納税を利用する

ふるさと納税は簡単に説明すると、税金の前払いをすることで納税した自治体より返礼品を受け取る仕組みです。
納税する自治体は自由に決められ、返礼品も自治体によって異なります。
返礼品は寄付額の約30%が目安となっており、トイレットペーパーや食材などの返礼品であればその分の節約が可能です。
例えば、3万円の寄付をした場合は1万円前後の返礼品を受け取れます。
寄付額には上限があり、年収や家族構成により変わるので詳しくは各ふるさと納税サイトでシミュレーションしてみて下さい。
仮に年収が350万円、独身または共働きの場合だと寄付上限は34,000円です。

まとめ

最後に、
- 固定費削減
- クレジットカードの利用
- ふるさと納税
それぞれどの程度の節約が可能か簡単にまとめました。
| 1ヶ月 | 1年 | 5年 | 10年 | |
| 住居費用 | 10,000 | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 |
| 水道光熱費 | 1,000 | 12,000 | 60,000 | 120,000 |
| 通信費 | 4,000 | 48,000 | 240,000 | 480,000 |
| 保険料 | 5,000 | 60,000 | 300,000 | 600,000 |
| ポイント | 1,500 | 6,000 | 30,000 | 60,000 |
| ふるさと納税 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 合計 | 21,500 | 256,000 | 1,280,000 | 2,560,000 |
表は仮定ではありますが、人によっては10年という長い期間で考えると256万円もの節約が可能になります。
これらは食費を切り詰めたり、電気をこまめに消したりすることなく、実現できます。
楽しく節約しながらお金を貯められるので、無理せず継続ができるでしょう。
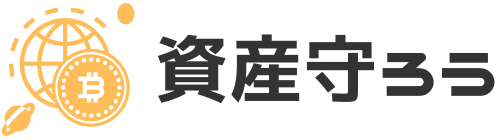









コメント