「一人暮らししているけど、なかなかお金がたまらないな・・・。」
「将来に向けてお金を貯めていきたいけど、何かいい方法は無いのかな。」
こういった悩みを抱えていらっしゃる方は多いと思います。
今回は一人暮らしでも上手に貯金をしていく方法をご紹介します。
同世代の方がどれくらい貯金をしているのか等、参考になるデータも合わせてご紹介いたします。
今後の生活を考える上で参考になるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
世代別の平均貯金額
| 平均値 | 中央値 | |
| 20代 | 113万円 | 8万円 |
| 30代 | 327万円 | 70万円 |
| 40代 | 666万円 | 40万円 |
| 50代 | 924万円 | 30万円 |
| 60代 | 1305万円 | 300万円 |
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和2年)」
世帯別の貯金額は上の図のようになっています。
平均値と中央値が大きく乖離していますね。
こういったデータの数字は上位層に引っ張られて、平均値が高くなってしまうことがよくあります。
より参考にすべき数字は、「中央値」であると言えるでしょう。
実際にこのようなデータを見て、どのように感じられますでしょうか。
「同世代の人もあまり貯金できていなみたいで、安心した。」と考えてしまうと、
今後、年金に期待ができない将来に対し、資金が不足してしまう可能性が高いです。
老後なんてまだまだ先と思われる方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、資産があれば嫌な職場でストレスを抱えながら働き続けなくても良くなるとも言えます。
今後、ストレスなくゆとりのある生活を送っていくためには、資産はどうしても必要になります。
まずは少しづつ貯金額を蓄えられるような仕組みづくりを行いましょう。
貯金の基礎

ここからは、貯金額をどう増やしていくかを考えてみます。
まずは、貯金の基礎的な部分から考えていきましょう。
貯金額をシンプルな計算式で表すと、このような式になりますね。
収入ー費用=貯金額
左辺を要素で見ていくと、①収入と②費用という観点に分けられます。
①収入 をすぐに増やすことは正直難しいですが、
②費用 を減らすことには、比較的簡単に取り組むことができます。
費用の削減方法
ここからは、費用の内訳を考えていきましょう。
費用額についてもシンプルな計算式で表してみます。
費用=変動費+固定費
右辺を要素で見ていくと、①変動費と②固定費という観点に分けられます。
①変動費 は知り合いとの食事等、交際費をイメージしていただけると良いかも知れません。
毎月の支出額が少し読みづらい部分ではありますが、少しの意識でも節約効果が大きくなる分野です。
例えば、コロナ禍の現在では自然と実践できている方も多いかも知れませんが、
月に1回飲み会に参加しないだけで、人によっては月々5,000円〜10,000円ほどの節約になります。
年間であれば、60,000円〜120,000円の節約と言えますね。
②固定費 は通信費や各種会員費等が代表的でしょうか。
正直、一番ストレスなく節約効果が持続する分野です。
例えば、3大キャリアとWi-Fiを利用している方の場合だと、
携帯各種料金(7,000円)+Wi-Fi料金(4,500円)=通信費(11,500円)
という計算になります。
しかし、1分1秒を争うような最高品質の通信環境までを希望していない方の場合ですと、
通信費用を格段に安く抑えることが可能です。
下記2点の実践を検討してみてください。
- まずは3大キャリアから、格安simに切り替える
格安simであれば、データ使い放題で 税込3,300円以下というものもあります。
データ使用量が少ない方であれば、そもそも0円(通話料等はかかる)というプランも存在します。
3大キャリアの平均費用から考えても、半額以下になりますね。
ただ皆様のお住まいの地域が、各会社の利用可能地域に該当しているかは、よく確認が必要です。 - Wi-Fiを解約する
Wi-Fiを手放すと、PC等の通信機器はどうするんだと感じられるかも知れませんが、
上で説明した格安simには、テザリング機能がついているものがあります。
テザリング機能があるスマートフォン経由で、インターネット接続は可能になるのです。
つまりテザリング機能が付いていて、データ使い放題の格安simスマートフォンを準備できれば、
人によってはWi-Fiは必要なくなります。
上記2点を実践した際の費用を見てみましょう。
テザリング機能付格安simスマートフォン(3,300円)=通信費(3,300円)
このような結果になりました。元々の通信費(11,500円)と比較すると、
月々8,200円が削減できました。70%以上の削減効果です。
とても効果的な削減ですね。
ここまでで取り上げてきた、飲み会代と通信費の削減だけで、月々10,000円は捻出できそうです。
貯金額へのアプローチ

さて、費用の削減について考えましたが、ただ貯金額を増やすことだけで終わってしまうと、
まだ資産形成に向けた取り組みの半分程度しか完成していないと言えます。
ここで上項で示した式にもう一度立ち返ってみましょう。
収入ー費用=貯金額
ここからは貯金額にアプローチしていきます。
上項の費用削減を実行し、月々10,000円捻出できたとして、そのお金をどうしましょうか。
利息が0.002%の定期預金にするのでしょうか。
それももちろん間違った発想ではありません。
しかし、せっかく捻出したお金です。
お金に働いてもらう感覚で、長期的な資産形成に取り組むのが有効でしょう。
幸いにも今は、国が資産運用を推進してくれている制度である、
つみたてNISAやiDeCoといった制度があります。
どちらも月々1万円等、掛金を決めて資産を運用していく制度です。
実際の運用効果のシミュレーションを行ってみましょう。
世界全体に分散して運用を行う株式投資信託の場合ですと、
年間の平均利回りは7%程と言われています。
ここではデータより少し控えめに見積もって、平均利回り5%で計算してみましょう。
節約で生み出した毎月10,000円を年間平均利回り5%で20年間運用した場合、
10,000円×12ヶ月×20年=2,400,000円 の元本に対し、
1,710,000円のリターンが見込める計算となります。
もちろん短期的にはリーマンショックやコロナショックと言ったような下落に巻き込まれることは、
何度もあると思われます。
しかし、つみたてNISAもiDeCoも毎月一定額を買い付けていく、ドルコスト平均法を活用できます。
これは相場が下がれば、同じ値段で口数を多く買えるというものです。
つまり、暴落時にはお得に買い増すことができると言えます。
上記シミュレーションからも分かる通り、長期的な資産運用の効果は非常に大きいです。
世界経済の成長を取り込み、お金に働いてもらう感覚で資産運用を行いましょう。
つみたてNISAやiDeCoの概要については、別記事での解説があります。
こちらにリンクを準備していますので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。
まとめ

ここまで、おすすめの貯金方法をご紹介しました。
貯金への取り組みのスタートは、何と言っても支出額の削減です。
少しの工夫で、継続的な削減効果が見込めるポイントを重点的に見直しておきましょう。
そして、節約して捻出したお金にも働いてもらいましょう。
そうすることによって、資産形成のスピードは格段に上がります。
運用にリスクは付きものであり、自己責任とはなってしまいますが、
長期的な積立運用であれば、リスクも軽減できます。
今後心身ともに豊かな生活を送るためにも、楽しみながら資産形成を行っていきましょう。
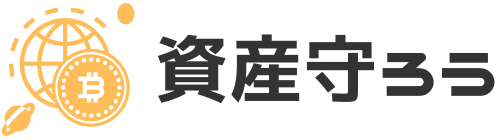



コメント